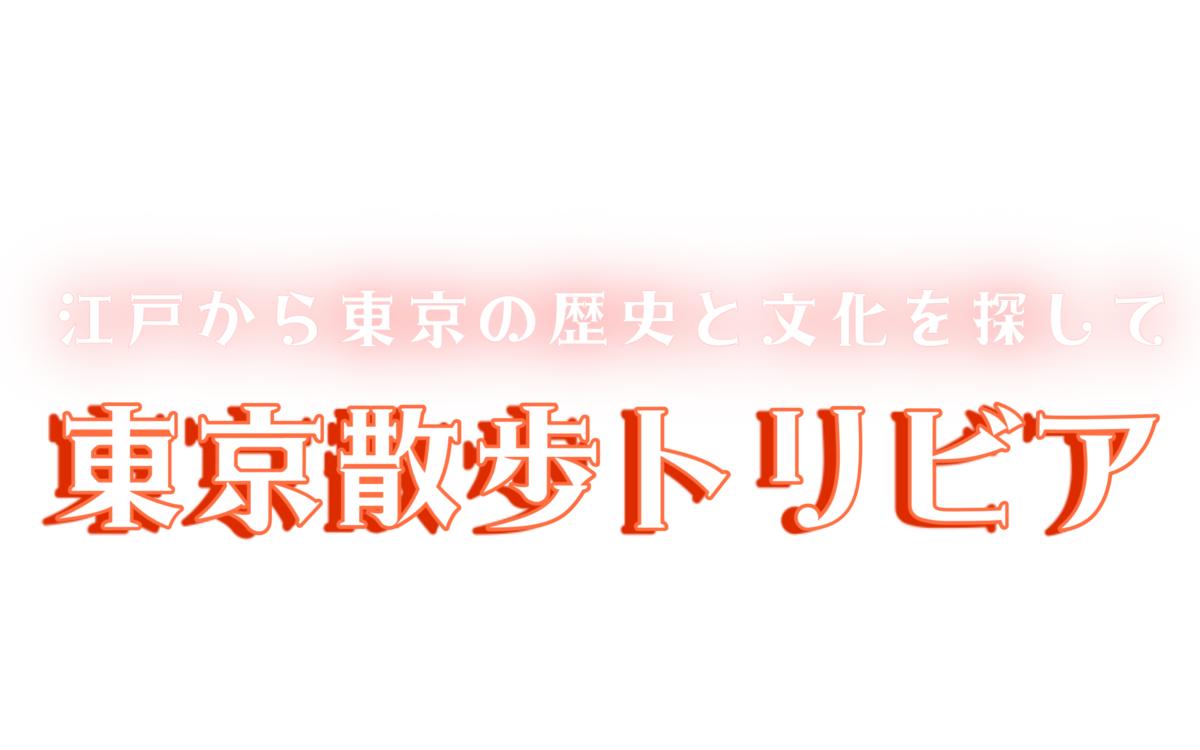Trivia!
閻魔様が子ども食らう伝承がある
三日月の形は女神の処女性を表す?
前編はコチラ
新宿二丁目。そこは江戸時代、内藤新宿と呼ばれた賑わいある宿場町でした。
太宗寺は内藤新宿の由来となった高遠藩内藤家の菩提寺で、江戸三大閻魔(善養寺、華徳院、太宗寺)のひとつで知られた浄土宗の寺。
正式には霞関山本覚院太宗寺(かかんざん ほんがくいん たいそうじ)といいます。
こちらのお寺、謎めいた伝承と歴史ミステリーが随所にあって大変興味深いのです。
子どもを食らった閻魔様
太宗寺の閻魔像には「つけ紐閻魔」という伝承があります。
江戸時代、内藤新宿には飯盛女(めしもりおんな)と呼ばれる遊女がいたことと関係するのかもしれません。赤子を預かり、子守りをしたとある乳母の話です。
赤子を背負って太宗寺境内で子守りをしていた乳母。
ところが子どもは泣いてぐずり、静かにはしてくれません。
「そんなに泣いていると閻魔様に食べられますよ」
乳母は、そう子どもに語りかけました。その時です。突然、乳母の背中が軽くなったのです。後ろを見ると赤子の姿がありません。
乳母は必死で子どもを探し、閻魔堂をのぞき見ます。
そこで見た光景は、あろうことか、閻魔様の口からおんぶ紐が垂れているものでした。閻魔が子どもを食らっていたのです。

なんとも不気味な怪談ですが、この話、じつは太宗寺の閻魔像に固有のものではなかったようです。『つけ紐閻魔』とそっくりの話が蔵前の閻魔にもあったと、長尾豊(1889~1936年)が『伝説民話考』に記しています。しかも、蔵前のほうが太宗寺より先にあった話だといいます。
その発端は分かりませんが、閻魔が子どもを食らう話の原型は蔵前、もしくはほかのどこかの土地にあったのでしょう。それが太宗寺の閻魔像でも語られるようになったと考えられます。
内藤家とは隠れキリシタンだったのか
太宗寺が大名である内藤家の菩提寺(四代・内藤正勝から)である以上、両者の関係を切り離すことはできません。
内藤家の家紋は「下り藤」と「左十字」。十字だからキリシタンとは安易に過ぎますが、昭和27年(1952)、太宗寺の内藤家墓所から織部灯籠(おりべとうろう)が出土しました。

織部灯籠は別名をキリシタン灯籠といいます。その原型は桃山時代から江戸初期に活躍した茶人で武将の古田織部(ふるたおりべ/1543~1615年)が考案したもの。
四角柱の竿石の上部にふくらみがあり、十字架のように見えること、竿石の下部には立像が彫られることなどが特徴です。
竿石下部の立像は地蔵に似せたマリア観音ともいわれ、隠れキリシタンの信仰対象と結びつけられることの多い灯籠です。
しかし、織部灯籠に関しては様々な研究があり、そもそもキリシタンの信仰とは関係ないとする説が現在は優勢であることを付け加えておきます。
内藤家の墓から出土した織部灯籠は本堂に向かって右手の社務所入口付近で見ることができます。
額に銀の三日月を戴く三日月不動(考察)
太宗寺境内の見どころはほかにも。
不動堂には額の上に銀製の三日月を戴いた珍しい不動明王の立像があります。

江戸時代に制作されたものだそうですが、その詳細は不明で、次のような伝えが残されているのです。
「この像を高尾山薬王院に奉納するため甲州街道を運搬していたところ、休憩のために立ち寄った太宗寺の境内で、盤石のごとく動かなくなったため不動堂を建立し安置した」
額の上に三日月があるのは「弦月の遍く照らし、大空をかける飛禽の類に至るまで、あまねく済度せん」との請願によるもの。
不動堂の屋根には天窓あり、日光や月光が差し込むと銀製の三日月が輝くように工夫されているとのことで、三日月に特別な意味を持たせたお不動様だということが分かります。

気になるのは「高尾山薬王院に奉納しようとした」とするくだり。太宗寺境内に三日月不動があることをもっともらしくする伝えに聞こえるのは勘ぐりすぎでしょうか。
なかなか意味深なお不動様なのです。
ここから先は余談。額に三日月を戴く像容は西洋文化にも見ることができます。
下の絵はローマ神話の女神・ディアナ(アルテミス)を描いたもの。ディアナとは処女神で狩猟と月の女神です。ギリシャ神話のアルテミスと同一視されています。


注目したいのはディアナの額。三日月を戴いていることがわかるでしょうか。
他の画家が描いたディアナを見ても、額に三日月を戴いている姿があります。



この三日月はディアナのアトリビュート(描かれた人物を示すための持物)として描かれ、処女性の象徴ととらえることができます。
次にこちらは聖母マリアを描いた『無原罪の御宿り』。

『無原罪の御宿り』バルトロメ・エスデバン・ムリーリョ(ルーブル美術館所蔵)
カトリック教会の教義では、マリアが処女のままでイエスを産んだように、マリア自身もまた性交という原罪なしに生まれた神聖な存在であるとされています。
足元に細い三日月が見えますね。
新約聖書の「ヨハネの黙示録」の「天に大きなしるしが現れた。一人の女が身に太陽をまとい、月を足の下にし、頭には十二の星をかぶっている」という一節に由来するものとされますが、この三日月はまさしくディアナのアトリビュートと同じではないでしょうか。
太宗寺の三日月不動が額に戴く銀製の三日月。これはいったい何を象徴しているのでしょうね。
想像は自由です。江戸六地蔵、閻魔、奪衣婆、キリシタン灯籠、そして三日月不動。先人たちの「想像」が息づく場所、それが太宗寺の境内なのだと思います。
まだ訪れたことのない方には、ぜひおすすめしたい場所です。