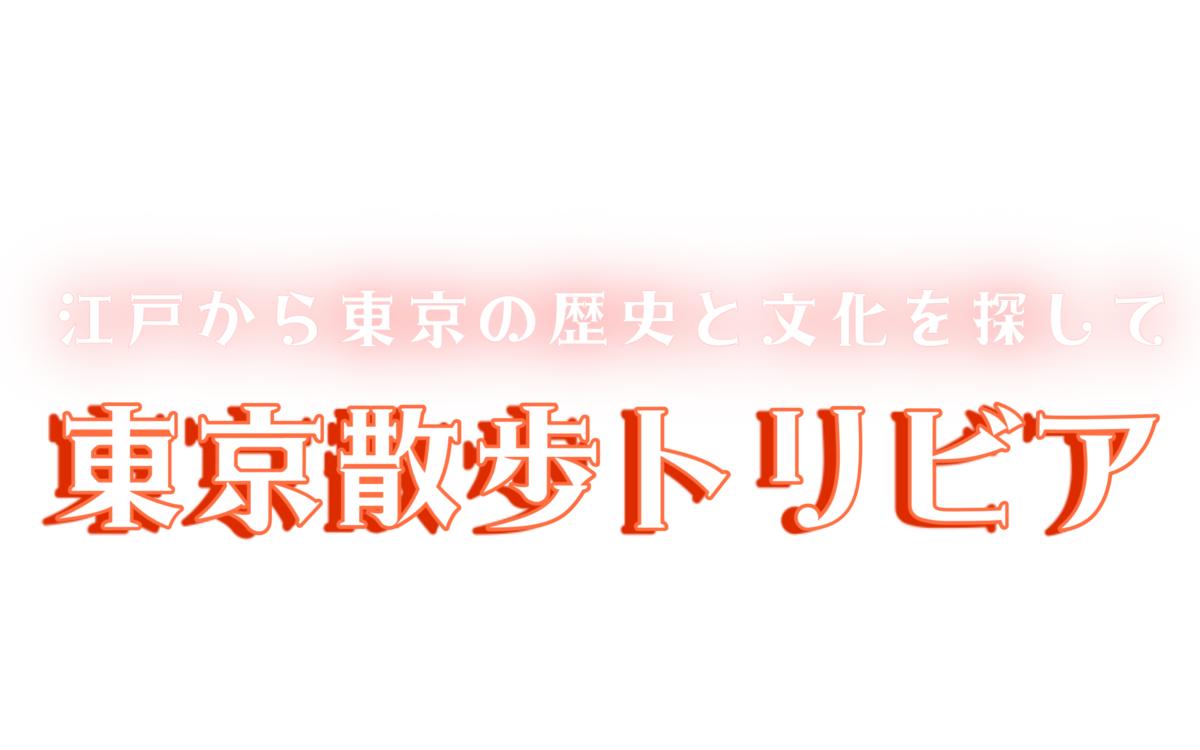天保3年(1832)、内藤新宿の太宗寺門前にある蕎麦屋で江戸を騒がす事件が起きました。
雇われていた奉公人の男が蕎麦屋の二階で出産したというのです。
男が赤子を産んだ!
前代未聞のできごとに居合わせたみなが驚きます。
その男の名は竹次郎こと「たけ」。
たけは、江戸の閉鎖的な社会で男性として生きようともがいた悲運の女性でした。

藤岡屋が残した竹次郎の記録
たけの存在を初めて知ったのは、当サイトでもたびたび登場する江戸の情報屋こと藤岡屋由蔵(須藤由蔵)の『藤岡屋日記』においてでした。
第一巻の天保三年の項に竹次郎の記録があります。
藤岡屋は江戸の噂話や瓦版、公的な文書などの膨大な情報を集めて記録し、売りさばいた人で、竹次郎の存在を最初に記録したのが『藤岡屋日記』でした。
その内容は竹次郎の「事件」を知った町名主が、町奉行に事の顛末を報告した文書。そこに竹次郎の生い立ちも記されています。
竹次郎こと「たけ」は山王町火消の娘として生まれたが、幼少期に両親を亡くし、親類の世話で成長した。
12,3歳になったころ、武州八王子宿の鯛屋という旅籠(はたご)に年季奉公に出た。しかし、飯売奉公(めしうりほうこう)に耐え切れず、この旅籠を逃げ出した。
江戸へ出ると、月代(さかやき)を剃り、男の身なりをして、新吉原の台屋(遊郭で商売する仕出し屋)に料理を届ける煮売り屋で料理を運び賃金を得ていた。
また、8月10日より、深川永代寺門前仲町の半七という者を保証人にして、太宗寺門前の蕎麦屋で雇われていたが、同月29日、突然腹痛を訴え、蕎麦屋二階で介抱していたところ、男子を出産した。
たけは普段、半纏を着て、股引をはいており、銭湯は男湯へ行っていた。その恰好もふるまいも女とは思えなかった。
と、このような内容が書かれています。
飯売奉公という言葉が分かりにくいかもしれません。「明治時代、新宿二丁目に牛の牧場があった? 大繁華街・新宿が昔はド田舎だったという話」の記事のなかでも書きましたが、たとえば内藤新宿の旅籠には飯盛女(もしもりおんな)と呼ばれるいわば遊女がいました。

飯盛女は街道の宿場町に置くことをなかば公認された遊女で、飯売女も同義と考えてよいでしょう。
直接的な動機は記されていませんが、たけは男の客をとることが耐え切れず、八王子宿の鯛屋を逃げ出していたのです。
そして、吉原界隈の仕出し屋への料理運びをしていたと。しかも、どうやら男の身なり、ふるまいをして周囲をあざむき、男性として仕事を得ていたようなのです。
女のふるまいを嫌うたけが出産した悲しい理由
藤岡屋日記のほかにもたけを記録した史料があります。江戸の裁判記録ともいうべき『御仕置例類集』で、この史料は国立国会図書館デジタルコレクションで見ることができます。
たけに関する記述があるのは「天保類集 女之部 火附盗賊之類」の項。
原文について興味のある方は下記画像をご覧ください。



一部を抜粋してみましょう。
「女子之所業を嫌ひ」
「自分と髪を切、若衆に相成」
「被尋出間敷(たずねいだされまじく)と野郎ニ姿を替え」
このように書かれていることから、たけが女性のふるまいを嫌っていたこと、自ら髪を切って若衆の姿をしていたこと、鯛屋から逃亡したときには、見つからないように男の姿をしていたことが分かります。
平素のふるまいがすでに男性と変わらなかったのでしょう。だから、太宗寺門前の蕎麦屋でも男として雇われたのだと想像できます。

しかし、なぜ、女であることを嫌うたけが妊娠することになったのか。その答えも同史料に記録されていました。
関係する箇所を要約すると
ある時、酒を一緒に飲んでいた男に、たけが女であることを見破られてしまう。
その男は「お前の正体を言いふらす」とたけをゆすり、性的な関係を強要した。
奉公先から逃げて身分を偽って生きているたけは、やむをえず、その男の言いなりになった。
蕎麦屋の二階で出産した経緯がこれではっきりとしました。
生まれた赤子は死んでしまい、人として恥ずかしく、世間に顔向けできないとたけは語ったようです。
この悲しい話が「火附盗賊之類」という盗みの処罰に関する項にある理由は、たけが知人宅の帯を盗んだこと、出産後に蕎麦屋の合羽を盗んで逃亡したこと、古着商をだまして衣類をごまかし取って質屋で金に換えた罪で捕まったことによります。
これに男女の密通や男装についての罪状が加わります。
結果、たけに科せられた刑罰は小伝馬町牢屋敷(江戸の囚人を収容した施設。吉田松陰が投獄、斬首刑となったことで知られる)に50日間の入牢と罪人の印となる入れ墨でした。
もちろん今後、男装することは禁じられました。
牢屋敷を出た後も、たけは男として生きた
小伝馬町牢屋敷を出たあと、たけの行方ははっきりしません。
しかし、その5年後、天保8年(1837)の『御仕置例類集』に再び「たけ」の名を見ることができるのです。
「天保類集 女之部 人倫を乱し候もの」の項です。
原文に興味のある方は下記の画像をご覧ください。





かなり長いので気になるポイントを抜粋して現代語に意訳します。
先だって、小伝馬町牢屋敷に入牢したとき、今後、男の姿で徘徊してはいけないと申し付けた。
しかし、また男の姿をして二回も召し捕らえられている。ほかに悪事を働いてはいないが、男装を禁じたのにまたもや男の姿で立ち回っているではないか。
つまり、小伝馬町牢屋敷から出たあとも、たけは男の姿でいることをやめなかったのです。
そして、再び捕らえられた理由が続きます。罪状は大きく二つ。
ひとつが、奉公先から金か何かを持ち逃げした奉公人を脅して、口止めに謝礼金を受け取ったこと。
ひとつが、他人同士の金の貸し借りのトラブルを仲裁する際に、たけが自らの身分を火附盗賊改配下の手先と偽ったこと。
これらの罪状により、たけに下された判決は死刑についで重い刑罰である八丈島への遠島でした。
たけの犯した罪がそれほど大きな罪だったとは思えないのですが、「人倫を乱し候もの」という言葉が流刑となった理由を表しているのかもしれません。
25歳の若さで流刑地に散った命
飯売奉公先の鯛屋を逃亡してからとういうもの、たけに安息の時はあったのでしょうか。居場所のない江戸で心休まることなく、もがくように生きていたのではないでしょうか。
八丈島に送られると、たけは鍛冶屋で働いたといいます。本来は女人禁制の仕事ですが、男として、竹次郎としての居場所があったのかもしれません。
八丈島へと到着したおよそ一年後、たけは病死しています。
数え年で25歳の若さ。
彼女の生涯を想うとき、トランスジェンダー(出生時の性別と自認する性が一致しない人)という言葉が脳裏をよぎると思います。
しかし、現代とはまるで秩序や価値観が異なる江戸時代のこと。
女に生まれ、その性を拒否したかのように生きた彼女の本当の苦しみを推し量ることはできず、ここでは想像の言葉を排除したいと思います。
たけの人間像についての考察は、女性史研究で知られる長島淳子氏の『江戸の異性装者たち』に詳しいです。ご興味のある方はぜひ読んでみることをおすすめします。
参考資料
『江戸の異性装者たち』長島淳子著 勉誠堂出版
『藤岡屋日記』
『御仕置例類集』