Trivia!
江戸時代、男女の心中は重罪だった
地獄の鬼婆が遊女の信仰を集めた⁉
歌舞伎町にひっそりと鎮座する「鬼」の神社。
内藤新宿の悲しき投げ込み寺にたたずむ地蔵様。
人食い伝承の大閻魔像。
愛する夫に毒殺された『東海道四谷怪談』の主人公、お岩さん。
新宿を起点に始める今回の散歩テーマはディープスポット。稲荷鬼王神社の次に訪れるのは遊女の投げ込み寺として知られる成覚寺と明治期に遊女からの信仰が篤かった太宗寺です。(「鬼」の神社についてはコチラの記事をどうぞ)
心中した男女の名が刻まれた台座
江戸時代、甲州街道の宿場町として栄えた内藤新宿。宿場内の旅籠には春をひさぐ遊女(飯盛女/めしもりおんな)がいました。
彼女たちが背負った運命は過酷なもので、梅毒をはじめ、さまざまな理由で命を落とす者がいたといいます。
その死は悲しいものです。
一般的に遊女には個別の墓がありません。いわば共同墓地に投げ込むように葬られ、無縁仏として土に還ります。
多くは借金のカタに売られてきた女性たち。
貧しい親に生まれ、親兄弟のために遊女となり、望まぬ日々の末路が投げ込み寺だとすれば、彼女たちにとってこの世とはなんだったのか。
さて、新宿二丁目へ。
内藤新宿の遊女が死ぬと投げ込まれた寺、それが成覚寺(じょうかくじ)です。前回の記事の稲荷鬼王神社から歩いて15分ほどのところにあります。

靖国通りに面した寺門はうらさびしく、草木が茂る境内にどことなく暗いものを感じます。
宗派は浄土宗。
歴史的に見て、投げ込み寺と呼ばれる寺には浄土宗が多く、それというのも引き取り手のない無縁仏を供養する宗派が他にほとんどなかったのですね。
成覚寺の寺門を入ります。この寺の歴史的背景を知っているからか、境内への侵入を拒むような圧迫を感じます。
おそるおそる周囲を見渡すと、とても厳しいお顔をした地蔵様の存在に気づきました。旭地蔵です。

この地蔵様はもともと成覚寺の境内にあったものではありません。旭町(現在の新宿四丁目)付近を流れていた玉川上水の北岸に建立された地蔵でした。
昔は「夜泣き地蔵」と呼ばれたそうで、いわゆる俗信で子どもの夜泣きにご利益があると信仰されたのだとか。
しかし、旭地蔵が建立された本来の目的はもっと悲しいもので、寛政12年(1800)から文化10年(1814)の間に内藤新宿の宿場内で不慮の死を遂げた者たちの魂を供養するための地蔵だったのです。
旭地蔵の台座に刻まれた18名の戒名に注目してください。そのうちの7組は男女の戒名で、遊女と客のなさぬ仲による玉川上水での入水自殺だとされます。つまりは心中です。

江戸時代、心中は驚くほど重い罪だった
幕府は男女の心中を「相対死(あいたいじに)」と呼び、厳しい刑罰を科しました。
たとえば二人がともに死んだ場合、死体の埋葬は許されません。
どちらか一人が死にきれないこともあります。すると、生き残った者は殺人の罪で処刑されるのです。
二人がともに死にきれないこともあるでしょう。その場合は3日間の生き晒しの上、身分を剥奪し、非人扱いとされてしまいます。
なぜこれほど厳しい刑罰が科されたのでしょうか。その理由は、厳罰をもって対応せざるをえないほど男女の心中が頻発したからにほかなりません。
この世で結ばれぬならば、せめてあの世で。男女の心中がもはやブームといえるような状況が江戸中期に起きたのです。
その火付け役となったのが近松門左衛門の『曽根崎心中』でした。この物語は実際に起きたとされる心中事件を題材にしており、作者自身が「恋の手本」と称揚する作品。
「この世の名残、夜も名残。死に行く身をたとふれば仇しが原の道の露。一足づつに消えていく、夢の夢こそ哀れなれ」
冒頭の一文からして、じつに美しい情景を想起させます。
もちろん、男女の間にはそれぞれの物語があるわけですが、現在のように自由な恋愛が許された時代ではありません。
旭地蔵の台座に刻まれた7組の男女はこの世では結ばれることのない関係だったのです。
優しいお顔の地蔵様が多いなかで、異質に見える旭地蔵の表情は何を問いかけているのでしょうか。
流行神となった奪衣婆
成覚寺の裏手に太宗寺(たいそうじ)があります。
この寺はとにかく見どころが多く、なかでも江戸三大閻魔のひとつに数えられた閻魔像は必見です。
閻魔堂には堂内を照らす電灯のスイッチがあるので、忘れずに押してください。そうすればお堂の外からも格子越しに閻魔像を見ることができます。

もっと間近で拝観したければ、閻魔大王の縁日である1月16日と7月16日に訪れるとよいでしょう。この日は閻魔堂が開帳され、ふだんは格子戸で閉じられている堂内が一般に公開されます。
この開帳日というのは江戸時代、奉公先や嫁入り先から休みをもらって帰省や外出ができた藪入り(草深い土地へ帰る意)の日でした。地獄界では鬼さえ休むとされる日で「地獄の釜開き」「閻魔の賽日」と呼ばれた日でもあります。
太宗寺の閻魔像(1814年制作、1933年補作)といえば、子どもを食らった伝承や盗賊を捕まえた逸話もあって、江戸っ子にはもとより有名な閻魔です。
それが藪入りの日に開帳されるのですから、大変な数の参拝者で賑わったことでしょう。
しかし、今回は太宗寺の閻魔像ではなく、その隣に仕えるとても恐ろしい形相をした奪衣婆(だつえば)像について書きたいと思います。

この鬼婆は、地獄の入口である三途の川の渡し守で、亡者の着物をすべてはぎ取ることから奪衣婆と呼ばれました。
そんなおどろおどろしい鬼婆によもやのできごとが起きたのは嘉永2年(1849)のこと。
突然の奪衣婆ブームが起きて、江戸で大人気の流行り神となったのです。咳止めのご利益にはじまり、しまいにはどんな願いも叶えてくれる神様だと大評判に。
もっとも、このときのブームにあやかったのは成覚寺に隣接した正受院(しょうじゅいん)の奪衣婆像で、この寺はたいそう儲かったのだそう。
奪衣婆が遊女の信仰を集めたというが
太宗寺に奪衣婆像が安置されたのは明治3年(1870)のこと。正受院の奪衣婆人気に対抗したのかどうか、太宗寺の奪衣婆像は内藤新宿の妓楼(遊女屋)から人気を得ます。
奪衣婆は衣服を剥ぎ取りますから、客を脱がせてナンボの妓楼には商売繁盛のゲン担ぎです。
かくして内藤新宿の遊女たちも太宗寺の奪衣婆を信仰したと伝わるわけですが…。
しかし、過酷な運命を生きる遊女たちの願いが、単なる商売繁盛であったはずがありません。無事に年季が明けて自由の身になること、人間らしく、女性らしい生活を手に入れることだったのではないでしょうか。
吉原遊郭の投げ込み寺として知られる浄閑寺(じょうかんじ)の過去帳によると、郭内で亡くなった遊女の平均年齢は23歳ほどと、あまりに儚いものでした。

内藤新宿にしても、遊女たちの置かれた状況はさほど変わらないでしょう。
果たして彼女たちは、若くして無縁墓の土に還る遊女の現実を見つめながら、それでも遊里に生きる日々の終わりに希望を持ちえたのでしょうか。
なんともいえぬ物悲しさを抱えたまま、新宿二丁目を後に、次は四谷の於岩稲荷田宮神社へと向かいます。
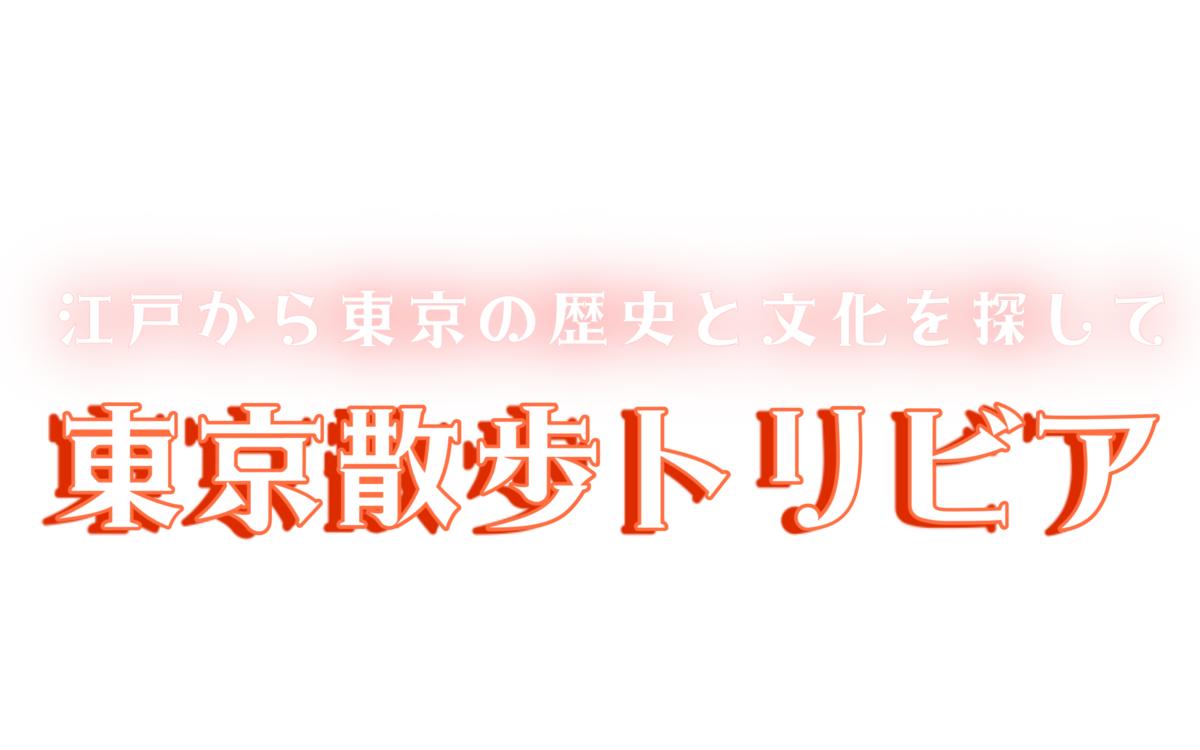


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2cb4bf26.553e71de.2cb4bf27.44960f2c/?me_id=1202898&item_id=10106813&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fglv%2Fcabinet%2Fnewsingle202210%2Fgga-95rak.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)




